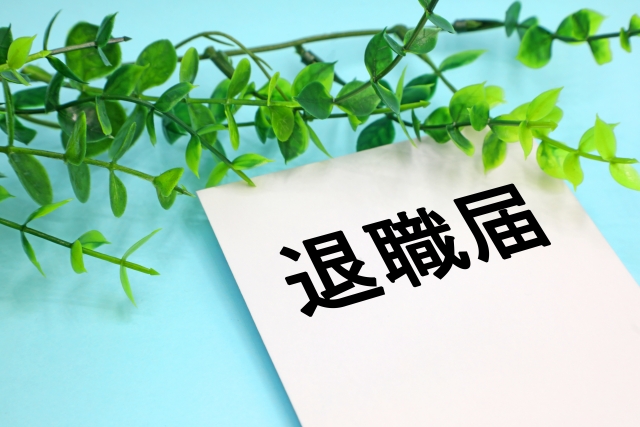代表取締役 河内信幸
§離職率の現状§
離職率の調査は、厚生労働省の基幹統計「雇用動向調査」などを通じて行われています。これは、全国の事業所を対象に毎年行われる調査で、従業員の入職者・離職者数を集計するものです。厚生労働省が2024年10月に発表した、2021年3月に卒業した新規学卒就職者の離職状況は、就職後3年以内を取り上げると、新規高卒就職者が38.4%(前年比1.4ポイント上昇)、新規大学卒就職者が34.9%(同2.6ポイント上昇)となりました。
これを事業所規模別でみると、従業員5人未満のところでは高校卒62.5%(前年比1.8ポイント上昇)、大学卒59.1% (同5.0ポイント上昇)ですが、規模が大きい事業所ほど離職率は下がり、1000人以上の事業所では、高校卒27.3% (前年比0.7ポイント上昇)、大学卒28.2% (同2.1ポイント上昇)となりました。また、業種別に見た離職率では高校卒・大学卒ともに、①宿泊業、飲食サービス業、②生活関連サービス業、娯楽業、③教育、学習支援業の順で高くなっています。さらに性別にみると、女性の離職率は男性よりも高い傾向が見受けられます。<https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00007.html>
§離職率の問題点§
特に、新卒社員の離職率は問題が多く、何パーセントから高いとは一概にはいえませんが、一般的に離職率が平均して20パーセントを超えると注意が必要だと言われています。厚生労働省の「雇用動向調査」の定義によれば、離職率は次のような式によって算出します。
離職率=離職者数÷1月1日現在の常用労働者数×100(%)
常用労働者とは、期間を定めずに雇用されている労働者、もしくは1カ月以上の期間を定めて雇われている労働者を指しています。ただし、この算定式では集計期間内に入職・離職した労働者が含まれないため、離職率が低く算出される点に注意を払う必要があります。
しかも、業種ごとに離職率の格差が広がっていることも忘れてはなりません。例えば、情報通信業や医療・福祉業では定着率が比較的安定していますが、宿泊業・飲食サービス業の離職率は依然として高い水準にあります。さらに、若い世代の離職率が高止まりしている背景には、職場環境の酷さや人間関係の複雑さを始め、労働条件全般に関わるミスマッチがあると分析されています。
(2025年11月27日)